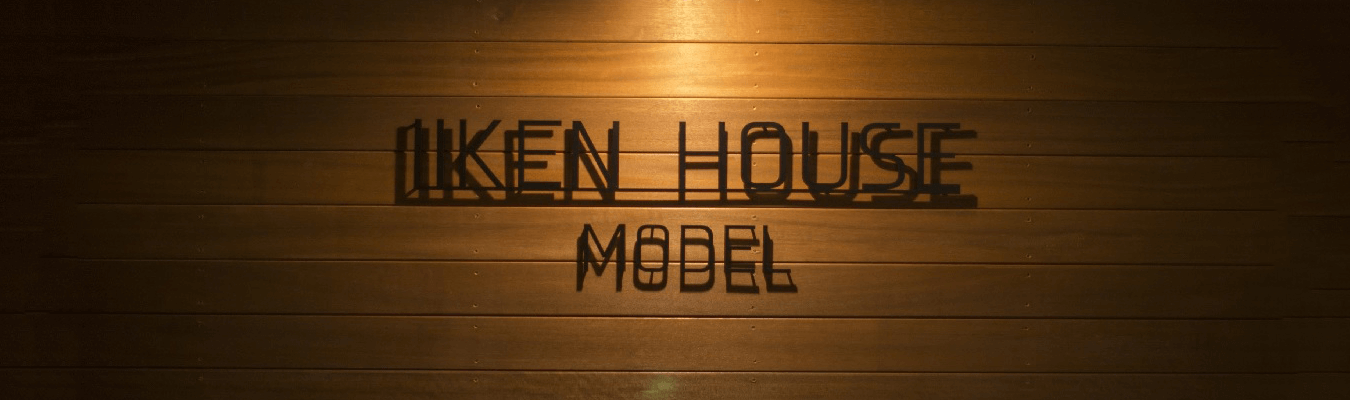いきなりですが、ご縁があって、先日、長野県でただ一つの藍染工房を訪ねる機会がありました。

工房は松本市の一角に、ひっそりと佇んでいましたが、創業はなんと明治44年。
以来、100年以上にわたり、天然の藍を使った「本藍型染め」を守り続けています。
生まれて初めて染物の工房を見学させていただきましたが、ご主人がそれはそれは丁寧に、藍染のことを語ってくださいました。
藍染は、発酵させた藍甕(あいがめ)を毎日手でかき混ぜ、布を何度も染め重ねる根気のいるお仕事。
また、発酵を維持するための温度管理も「薪」を使い、徹夜も辞さずに行うという、とても厳しいお仕事でもあります。

さらには、渋紙に文様を彫り、防染の糊を置いて染める「型染め」を取り入れられているそうで、この文様を彫った型紙も見せていただきましたが、気が遠くなるほど細かく繊細なお仕事でした。

こうして、たった一つの手間でさえ決して惜しまない「職人の技」が評価され、2024年には「松本本藍型染」として長野県の伝統的工芸品に指定されました。

お話を伺っていて、ご主人は、本物の職人らしく朴訥ではありますが、「藍」と真摯に向き合う気持ちが心の芯まで伝わってきました。
そして、写真をご覧ください。

お会いしたときから気になっていたのが、ご主人の指と爪。
これが、美しい「藍色」に染まっていました。
その手を見た瞬間、涙が出そうになりました。
「藍染」は、まさに「愛染」ですね。
以上です。