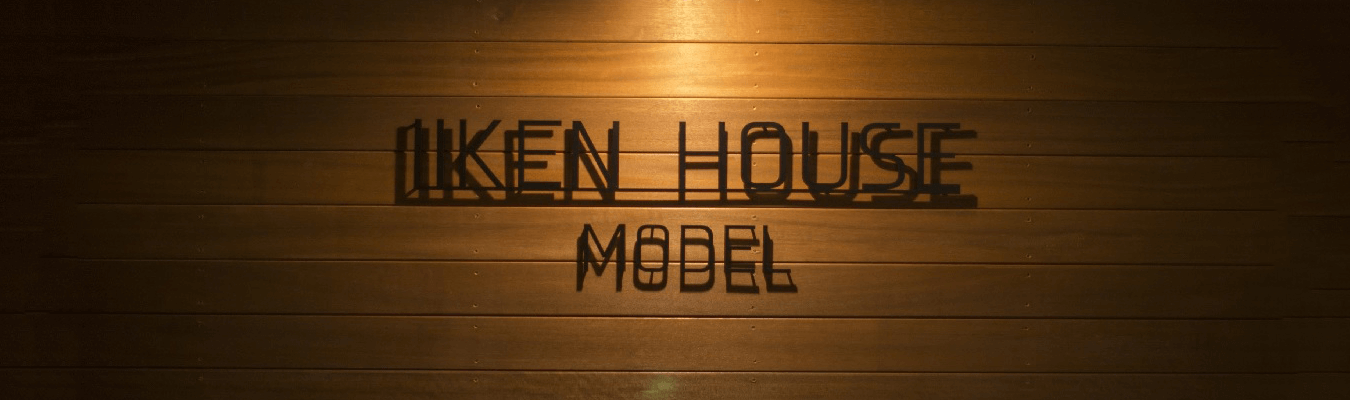いきなりですが、今朝のニュースには少し驚きました。
というのも、「潮時」の本来の意味についてのお話です。
生まれてこのかた「潮時」といえば「止め時」や「辞め時」という意味で使っていたのですが、これがなんと、本来は「ちょうどよい時機」とか、またとない「好機(チャンス)」や「最適なタイミング」を指す言葉だったとニュースで伝えていたのです。
なので、これまで私が使っていた「潮時」は、すべて間違えて使用していたことになります。
そこで、いちおうGoogle先生に聞いてみたのですが、「潮時(しおどき)」は、もともと潮の流れが変わる時刻や、漁や船出に最適な潮の時間という意味で、そこから転じて日常的には物事を始めるのにちょうどよい時機というより、物事を終わらせたり区切りをつけるのにちょうどよい時機、要するに「終わり」に最適な時期の比喩表現として使われるようになった、と。
繰り返すようですが、私は「終わり」の比喩として、50年近くこの「潮時」を使用してきたわけです。
まあ、ほとんどの皆さんも「潮時」の使い方は、私と同じだったと思います。
ただ、そうかといって、今日から突然「潮時」を本来の意味で「これは、またとない潮時ですねー」なんて使いはじめたら、「えっ?」、なんて感じで、まわりから怪訝な顔をされそうなので、しばらくは世間の様子を伺いたいと思っています。
嗚呼、小市民。
失礼しました。
以上です。