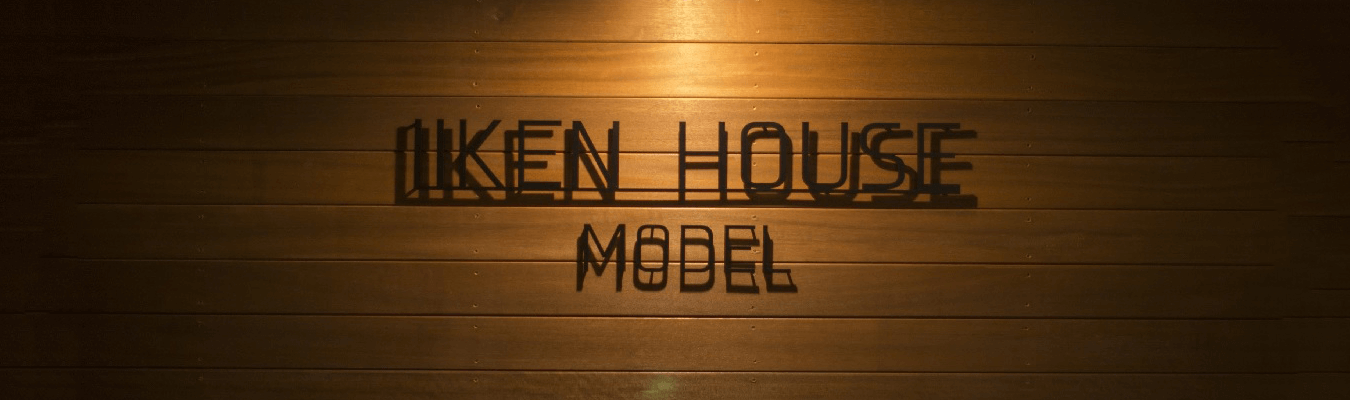いきなりですが、過日は能登地方の現況確認を兼ねて北陸地方を2泊3日で視察して参りました。
能越自動車道から被災地を見ると、未だブルーシートに覆われた家が点在しているのがよくわかりました。
気持ちとしては、「既に被災から1年が経とうとしているのに、いったいどうなっているの?」と思う一方で、このようなことを書くのは被災された方々に対して正しいか否かは自分でも判断が付き難いわけですが、一口に復旧復興と言っても、過疎化がどんどん進行する地域をどのようなかたちで復興して行くことが正しいのか・・・?
仮に、手あたり次第無計画に復興を進めたら被災地域の人口一人当りに対する復興費用は、恐ろしい金額になってしまうと思います。
では、予算の面だけを切り取った合理性に基づき、「ふるさとや愛着のある地域を捨てて、快適な住居を用意するからこちらに移り住んで下さい。」と言うことが正しいのか?
まあ、この課題には簡単な答えはなく、地域の状況、復興の目的、社会全体への影響など、複数の要素を総合的に考慮する必要があるとは思っています。
ただ、私としては、まずは「復興」と「復旧」の違いを明確にすることが大切だと思っています。
要は、例え仮設であっても生活に必須なインフラの「復旧」は完全に行う。しかし、被災地を災害以前の状態に戻すだけでなく、それを超えて地域や社会の再構築、発展を目指す「復興」については、もう少し時間を掛け、地域や復興に対する考え方を広範囲にし十分な議論をして行くこと。その議論をさせて貰うこと自体の理解を被災者に得ることが大切かと思います。
実は我々も、令和元年の台風19号災害では関係者に重大な人災こそありませんでしたが、社員やその家族が被災しましたし、グループ会社の運営する施設も壊滅的な被害を受けてしまいました。
その後、悩みに悩んだ挙句、地域の皆様からの声を反映し、借入金と国の補助金を利用させて頂きながらなんとか施設の「復旧」を果たしました。
しかし、復旧後ほどなくして「地域の治水対策にはこの土地が必要。」との打診が国から寄せられたのです。これには驚きましたが、この地域の本質的な「復興」の為に「復旧」したばかりの施設を地域に拠出する決断をしました。
そんな経験から、私は「復旧」と「復興」は別なものだと被災者のひとりとして考えるようになったのです。
とても難しい課題です。
しかし、残念ながら我が国は潤沢な予算のある国ではありませんし、人口も減少に転じた国です。
なので、この答えは将来の為にもしっかりと出す必要があると思います。
以上です。